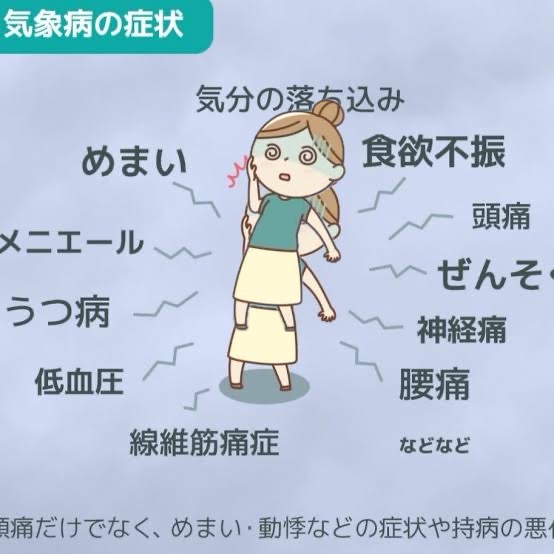こんにちは!立川デンタルクリニックすずきです☺️

今週は歯科助手の石井がブログを担当させて頂きます🦷
まもなく梅雨入りの時期となりますね☔️
さて、6月といえば”梅雨”のイメージが強いかと思いますが、6月は「虫歯予防月間」であることはご存知でしょうか?
これは、日本歯科医師会が6(む)と4(し)の語呂合わせにちなんで6月4日を「虫歯予防の日」に定めたこと。そして、そして厚生労働省や文部科学省が6月4日~10日までの一週間を「歯と口の衛生週間」としたことなどが元になっていると言われています!
幼稚園や学校でも歯科検診が増える時期でもありますよね🦷
当院の理念でもある、”口は身体の入り口”とあるように、口は健康の入り口でもあります👄生涯を通じて充実した食生活を送り、健康な身体で過ごすためには、歯と口の健康は欠かすことができません。
毎日の歯磨きなど身近なところを見直し、定期健診を受けて、むし歯や歯周病などの口の病気を予防しましょう!!!
この歯と口の衛生週間では、特に子ども達に歯磨きの基本を伝えると良いでしょう🪥
そもそも歯磨きは、歯垢と呼ばれるプラークを落とし、健康な歯を守ることが目的です。
プラークは最近の塊であり、歯と同じような乳白色をしているため見えにくくなっています。磨き残しがあると虫歯や歯周病につながる可能性があるため、プラークを磨き落とすことに注意しながら歯磨きをすることが大切です!
子どものときから口腔機能の健康状態を保つことで、言葉の発音や味覚の発達などにもよい影響を与えるだけでなく、口腔に関連する病気予防にもなり、将来的な医療費の負担も大きく軽減できるでしょう。
何歳になっても食事や会話を楽しむためには、毎日の歯磨きが重要と言っても過言ではありません!
そこで歯磨きの基本についてお話ししていきます。ぜひ、お子さんがいる親御さんは子どもたちに伝えて、一緒にやってみてくださいね🌈
[歯磨きの基本]
① 正しい磨き方で磨く
まず重要なのは正しい磨き方で磨くことです。磨き方がまちがっているとプラークをしっかり除去することができません!
正しい磨き方は、「歯ブラシの毛先を歯の先にあてる」「1か所あたり20回以上磨く」「適度な力加減で磨く」の3つがポイントです。特に重要なのが、力加減です。
ブラッシング圧が強ければ毛先が広がり、もう1つのポイントである「歯ブラシの毛先を歯の先にあてる」という部分も不可能となってしまいます…。
プラークは軽い力でも除去できるので、圧が強くならないように、細かい動きが可能な鉛筆持ちで歯ブラシを握ることもコツです💡
②磨き残しの多い部分に注意する
磨き残しの多い部分は…
🦷上奥歯の表側
🦷上下奥歯の裏側
🦷前歯の上 です。
「イ」の形となるよう口を横に大きく広げて、歯ブラシの動く範囲を広げることがポイントです👄
ブラシが届きにくい歯のすき間ケアには、歯間ブラシの使用も推進されています!
毎食後が理想ですが、1日1回使うだけでも良いのでまずは1日1回を目標にしてみましょう!
③自分に合った歯ブラシを選ぶ
歯ブラシは、商品によってヘッドの形状やサイズ、毛の硬さがそれぞれ異なります。サイズは、上前歯と同じくらいの大きさが目安です!
しかし、大きすぎると奥歯まで磨くことが難しくなるため、子どものうちは子ども用の小さい歯ブラシを使用しましょう🪥
また、大人・子ども問わず、歯茎が健康な場合は「ふつう」の硬さの歯ブラシ、歯茎が傷んでしまっている場合は「やわらかい」歯ブラシがおすすめです。
歯ブラシは使用するうちに毛先が傷んできてしまうので、1ヶ月ごとに交換すると良いです!
このように毎日行う歯磨きにも、知っておくと役立つことが沢山あります!
ぜひ、この期間を活用して歯磨きの大切さをお子さんと一緒に確認してみてください🌟
また、検診やクリーニングがご希望の方は当院にお問い合わせくださいませ☎️
お電話からでもWEBからでもご予約いただけます。
☎️042-512-5666
💻http://tachikawashika.tokyo/reserve/
立川駅南口から徒歩5分🚶🏻
🦷診療時間
【月水木金】9:30~13:30/15:00~18:30
【土】9:30~13:00/14:00~18:00
*火曜は訪問診療のみおこなっています。